- 友愛ホーム>
- 活動内容>
- 2024年度の活動内容>
- 2024年度OEJAB派遣員が語る抱負と期待
2024年度OEJAB派遣員が語る抱負と期待

千葉大学医学部5年
岩岡 優太

まずはこの度、自分の力ではとても得難いような学びの機会を頂ける事となり、大変有り難く思っております事をお伝えしたいと思います。
先日行われた事前勉強会ではクルド人問題に関するお話を伺うことができましたが、そのお話が非常に印象的でした。
クルド人とはそもそもトルコ南東部からイラク、イラン、シリアなどにまたがる地域に住む民族で、固有の言語も保有していますが、トルコ国内の体制においては弾圧を受けています。そうした背景から各国に難民として移住する人々が多いようです。
恥ずかしながら私自身は、クルド人の人々についても彼らの置かれている実態に関してもそれまでほとんど知らずに過ごして来ました。日本において難民問題というのはあまり焦点を当てられない部分ではありますが、日本にもクルド人は一定数在住しています。正しい理解をされないまま冷たい視線を浴びてしまう人もいると思います。知らなければ気づかないような問題は山ほどある一方で、それらに気づいている人が理解し発信し、焦点を当てて問題化すべきことがあるのだろうと痛感しています。
私は、現在大学では臨床実習生として、様々な理由で病院に来ている患者さんと接しています。医療や福祉の分野においても、一筋縄ではいかない問題がたくさんあります。この度の派遣ではオーストリアにて様々な福祉事業を展開しているOEJABの施設を見学する機会を頂けると伺っていますが、その中から日本に還元できる要素を見出し、それを直接見聞きし知ったものとして、いつか社会の一隅を照らす役割を担えたらと思います。
一緒に派遣に向かう5人の同期の皆はさまざまなバックグラウンドを持っていて、そんな皆さんとそれぞれの持つ知識や考えを一つのテーマに向けて交わし合うことを楽しみに思いますし、きっと刺激的なものになるのではないかと期待しています。
また、このプログラムへの参加を希望されながらも叶わなかった方々が数多くいらっしゃる筈で、其々が少なからず友愛の理念へ通じる理想や考えをお持ちだと思います。この頂いた機会で自身が得た知識と経験、感じたことを自分のものとするだけではなく、そのような方々への敬意も込めて、広く共有するために発信していきたいと考えています。
筑波大学人文・文化学群4年
須黒 正也
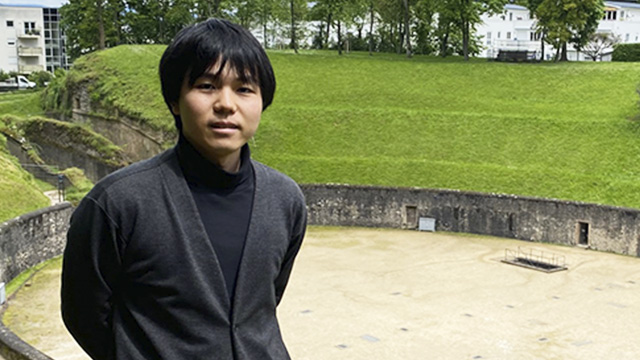
この度は2024年度OEJAB派遣員にご選出いただき、誠にありがとうございます。私一人ではなし得なかった、貴重な学びと経験の機会をいただき、大変嬉しく思っております。
12月の事前勉強会では、鳩山由紀夫理事長ならびに友愛事務局の皆さん、共にオーストリアへ向かう派遣員の皆さんに初めてお会いすることができ、その温かな人柄や高い向上心に大いに刺激を受けさせていただきました。
また、会では派遣に向けて前提知識となる「友愛」精神や、日本の友愛活動に影響を及ぼしたカレルギー伯、そして昨今耳目を集めているクルド人難民問題や台頭するポピュリズムについて、先生方のご講義を聞かせていただき、大変勉強させていただきました。
私は大学でドイツ近現代史を専攻しており、辺境地域のナショナリズム運動を専門分野としております。従いまして、国民国家が誕生する契機となったフランス革命の理念に「友愛」が含まれている意義を、ジョン・ロックの市民法、すなわち合意形成による熟慮民主主義を実現するという見方から解説された谷藤先生のお話など、大変興味深く拝聴致しました。
また難民問題につきましては、実際に最前線でご活躍されている大橋毅弁護士から日本におけるクルド人難民支援の実態や排斥運動についてお話いただき、フェイクニュースやデマによる日本社会と彼らの分断の深刻さ、入管による受け入れの厳しさを再認識致しました。
私はドイツに留学をした経験から、社会的マイノリティとして社会を見つめ直し、差別や偏見が現地社会へ溶け込むことを難しくしていると痛感しました。さらに、ウクライナ避難民の留学生の生活を支援した経験から、明文化されていない社会規範や、文化と言語を始めとする、外国人として日本社会と融和する難しさをかねてより問題視しておりました。
「郷に入っては郷に従え」という言葉を否定は致しません。ですが、だからといって村八分にせずに、「郷の掟」を彼らとともに共有するサポートが必要であるとより一層痛感致しました。
その問題意識を踏まえ、OEJABが行う難民支援活動が実施する支援策の実態を現地にて学び、現地の職員の方々との交流を通じて知見を深めさせて頂きたいと思います。また、この度の派遣事業だけでなく、今後も友愛ファミリーの一員として携わるためにも、同期の皆さん、そして事務局の皆さんとより交流を深めさせていただきたいと思います。
東京大学文学部社会学専修4年
坪山 倫

この度は、OEJAB派遣学生として選抜されたことを大変悦ばしく存じます。三月のウィーン渡航に向けた私の目標は、二つに大別されます。
第一に、訪問先の機関や施設において、最大限の学びを得ることです。今回の派遣においては、ウィーンに居を構える国際機関を訪問しそこで働く方々のお話を伺う機会や、難民施設を訪ね難民の方々を含む人々と直接のコミュニケーションを行う機会が用意されている、と伺っております。私自身、アカデミアや民間企業におけるキャリアを追究したのち、最終的には政府間機関における社会制度設計や公共政策業務に携わりたい、と思い描いています。そのような目標に照らして、今回の派遣における機関訪問は千載一遇の良縁であり、事前の準備を重ねた上で、そこでの学びを最大化することに努める所存です。
また、日本に閉じこもっている限り「日本の難民受け入れ状況に鑑みても」難民の方々と直接触れ合う機会というのは大変貴重なものです。私自身、ドイツおよびフランスに留学していた時期に、移民家系の友人を多く作る、あるいは街で移民の人々と触れ合うことはあっても、実際のところすぐ近くにいるはずの難民の方々と、コミュニケーションを取る機会には恵まれませんでした。施設において難民の方々に伺いたいことは山程ありますが、情報収集を主目的として派遣されるわけではありませんから、自分の研究や将来設計に対するインプリケーションの如何は措きつつ、彼らとフラットかつ丁寧に接し、その場において彼らに向き合うことができる、という事態そのものの大切さと悦びとを享受したいと考えております。
第二の目標は、ウィーンでしか、あるいはオーストリアでしか味わえない体験に、可能な限り多く従事することです。私は先にも言及した欧州留学中に、一度ウィーンを独りで訪れた経験があります。折しも十数年に一度の大雪に見舞われていた12月のウィーンで凍える思いをしていたことが振り返られます。今回は孤独な旅ではなく、素晴らしい仲間と共に渡航できることを嬉しく思います。大好物のシュニッツエルや、前回渡航時には挑戦できなかった本場のザッハトルテに舌鼓を打つことが今から待ち遠しく、シーレやクリムトの絵画に再会できることも、この上なく楽しみです。学部生活の最後に、最高の学びと思い出を得られることを、心から期待しています。
北海道大学大学院共同資源工学修士2年
佐々木 太一

この度2024年度OEJAB派遣に参加させていただくことになりました、北海道大学大学院工学院修士2年の佐々木太一です。多くの優秀な学生の中から私を選抜してくださり誠にありがとうございます。皆様のご期待に応えられるよう、今回のオーストリア派遣では多くのことを吸収したいと思います。
私がこの派遣に申し込んだ一番の理由は、グローバルな視点をもつ様々な分野の学生と深い交流をしたいと思ったからです。私は大学院で資源学を学んでおり、その視点から世界を見つめることがよくあります。一方、国際関係論や地政学といった知識はほとんどありません。今回の派遣では、このような私の知らない世界の見方について、様々な専門を持つ学生から学びたいと思っています。
先日の勉強会に参加した際、初めて一緒に派遣に参加するメンバーと会いましたが、私の期待はますます高まっています。講義に取り組む姿勢や質問の内容から、普段から物事を深く考えていることがうかがえました。また、彼らとの会話を通して専門分野の知見の深さと自分の意見をはっきりと持っていることがわかりました。このような優秀な学生と一緒に派遣に参加できることをとても光栄に思います。
また、勉強会・懇親会ではOEJAB派遣員の先輩方とお話しする機会があり、そこでも多くの刺激をもらいました。
参加されていた先輩方は、一人一人が友愛という団体がどうすればよりよくなるかを真剣に考えており、非常に頼もしく皆さんについていきたいという気持ちが芽生えました。私も今回の派遣を通じて、自分の知らない知見や考え方を吸収し先輩方に追いつきたいと考えています。
改めてこのように多様な人材が集まった友愛という財団に所属できることを非常にうれしく思います。私も今回の派遣で自分なりの「友愛」を見つけ、帰国後同期や先輩方と語り合うことができればと思っています。
最後になりますが、私がこの派遣の募集を見つけたこと、そして財団の皆様が私を選んでくださったこと、すべての縁に感謝し行って参りたいと思います。
京都大学総合人間学部3年
尾田 夏野

この度はOEJAB派遣員に選抜していただき、ありがとうございます。事前研修会も終え、友愛ユニオンの一員になれることを嬉しく思いつつ、近づいてくる渡航の日を楽しみにしております。
私がこの派遣プログラムに申し込んだ理由は、まさに難民問題と国際機関の果たす役割への関心にあります。私は平和や人権問題に関心を持っており、現在は国際法を勉強しています。国際法を勉強する中で常に感じるのが、マクロな視点だけで物事を見てはいけないということです。国と国との関係、紛争、膨大な数の移民・難民など、ニュースや授業で知る情報には、個人の顔がありません。過酷な現実の中で最良の判断を探るには、もちろん冷静な分析や利害の調整が必要です。しかし、どんな専門家でも、実務家でも、個人の重みを忘れず想像し続けることが必要だと思うのです。
この想像力を養うためにも、私は今回のオーストリア派遣の機会を最大限に活かしたいです。そのためにも、まず、渡航前にできる限り予習していきたいです。実際に目で見た時の学びや感動の大きさを決めるのは、事前の知識や期待です。オーストリアの難民問題、CTBTO、またオーストリアの歴史について、事前研修に加えて自分でもしっかり勉強しておきたいです。また、渡航中は、人との出会いに一つ一つ向き合っていきたいです。たとえ短い時間であっても、心に残る出会いを作ることは可能だと思います。難民施設で暮らしている人、職員の人、CTBTOで働いている人など、様々な人との出会いを楽しみたいです。そうすることで「難民問題」や「国際機関」は、目に見える、顔のある人の集まりとして想像できるようになると思います。
私は卒業後、海外の大学院に留学し、国際法を通じた平和な世界への規範形成について学びたいと思っています。自分の目で見て、耳で聞く経験は他の何よりも記憶に残ります。今回の派遣は、机に向かう勉強と現実の世界を繋げる絶好の機会です。多様な専門、関心を持つ派遣メンバーと一緒に、目一杯学んで帰ってきます。
東京科学大学6年
木島 優美

この度は、OEJAB派遣学生に選んでいただき、誠にありがとうございます。先日の勉強会やユニオン懇親会では、友愛活動の歴史を深く知ることができ、また友愛ユニオンの素敵なメンバーと交流する機会をいただき、派遣に向けて期待に胸が高鳴りました。そして何より、それぞれ異なる関心を持つ同期の派遣員と、お互いの視点を交換し合いながらオーストリアで学びの機会を得られることが、大変楽しみです。
私のビジョンは、「生きづらさを抱え、罪を犯した人が、今度こそ社会の中で共生して幸せな生活を過ごせるため伴走する」ことです。そのために、OEJAB派遣では、オーストリアにおける、様々な背景を抱えた人との共生の在り方を体感したいと考えています。難民支援、青年支援、介護福祉事業など、どんな人の幸せも諦めることなく、共生に向けて尽力されているOEJABの支援活動を実際に見学することで、ビジョン実現に向けたヒントを探していきたいです。また、可能であればOEJABの支援の下で過ごされている方たちにもお話を伺えたらと思います。
特に、難民支援については、出身国で大変しんどい思いをされた方が難民申請をするために日本に来ても、手厚いケアを受けるどころか厳しい環境で過ごさざるを得ない現状を、先日の勉強会で改めて実感し、大きなショックを受けました。さらに、たとえ難民認定を受けることができたとしても、日本で生きやすいようなサポートがなければ、彼らの苦難は終わらないだろうと感じます。一方で、難民問題には、戦争や紛争、差別、貧困など、様々な社会課題が絡み合っていますが、だからこそ難民に対する支援が広がっていけば、他の生きづらさを抱えた方たちも生きやすくなる社会に繋がるかもしれない、とも思っています。
二週間の派遣期間で、OEJABの取り組みを存分に吸収し、将来取りこぼしのない支援を行うための大きな一歩にしたいと考えています。そして、OEJABを一つのロールモデルとしながら、派遣後は私も友愛があふれるような世界を目指して、邁進していきたいです。
